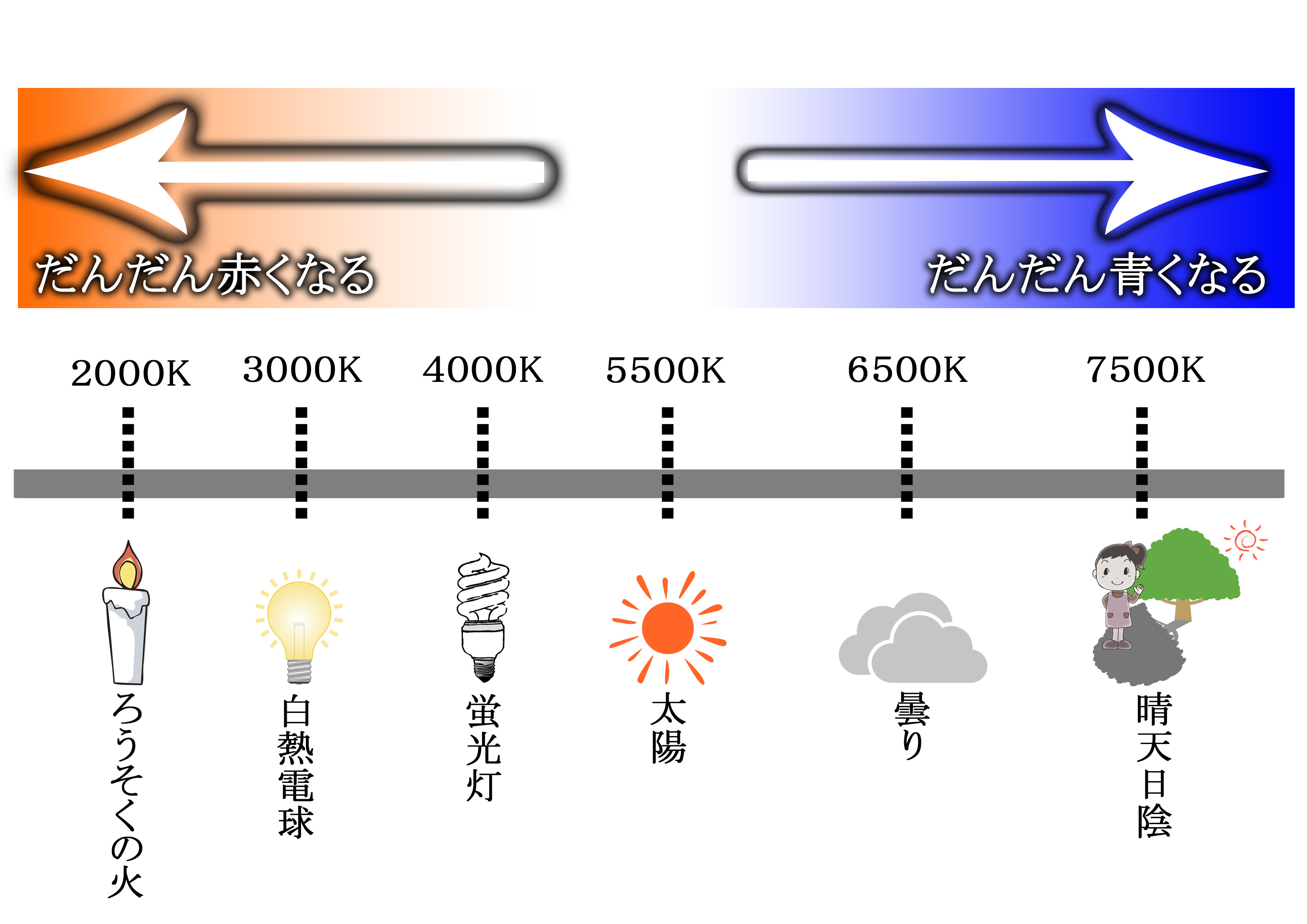色温度(ホワイトバランス)
色温度という言葉は、フィルムの時代では聞きなれない用語でした。
日常使用されている温度は摂氏で表し、固体(水・H2O)が液体となった時点を0℃とし、その液体
が気体と成った時点を100℃として、100等分にしたものが1℃です。
色温度計は産業界では高温領域で多く使用されています。
1)色温度Kとは
Kの記号(人名による)は絶対温度を表す記号で、マイナス温度273.14℃を0Kとします。
この温度以下は存在しない(原子・分子のエネルギーの活動が停止するため)。
「図1」は温度に対しての色の変化です。低い温度側の色は赤み、中間の5500K近辺では白色の
太陽光で、高温側に向かうほど青みが強くなります。
「図2・3」は温度に対しての色の変化です。温度が高くなるほど青味となります
2)デジタルカメラの色温度
デジカメの色温度及び画像ソフトの色温度は色が反対で、低温側が青味で、高温側で赤味です
(「画像A~C」)。
なぜこの様に色を反対色にしたのか、カメラの説明書では詳細には明記していません。
PXカメラの説明書では、低温側は赤色を抜いて青色とし、高温側は青色を抜いて赤色とすると説明
されています。
白い色をより白くすることと、色かぶりを修正するために色を反転しているとのことです。
次回その2(可視光線)に関連しているのでは?。
撮影時にRAWファイルの形式で撮影しないと、色温度の調整は出来ません。
図1 色温度表